お久しぶりです。今回のブログ担当の前田です。
第7回で触れたとおり新しいブログを開設する影響でこのページへの投稿は今回が最後になるかもしれません。ですが我々の活動そのものは今後も継続していくので、これからもよろしくお願いします!
さぁ、今回は春学期折り返しの第8回。ゼミ議論もいよいよ佳境です。
まず四限は恒例の批評理論入門。今回は「間テクスト性」「メタフィクション」「結末」の話です。
間テクスト性とはすなわち作中における他の文学テクストの影響・関連性のことをいいます。たとえば『フランケンシュタイン』は『失楽園』と間テクスト性の関係にあると言えます。神に作られし始まりの人類・アダムとその敵対者・サタン、両方のモチーフを怪物が有していることが作中で言及されます。
さらに描写の影響を受けた絵画から作品の解釈を広げるという読み方も可能です。
これに関しては五限でも言及されますので、詳しくはもう少し下までお待ちを。
メタフィクションとは語り手が読者へ向かって語りかけ、作品そのものを意図的に作り物であると明らかにする手法です。議論中で上がった例を一つ挙げれば『古畑任三郎』が最たる例でしょう。演劇用語では「第四の壁の破壊」とも言うそうです。
この項目では「距離」という要素がかなり頻出します。フランケンシュタインもその形式上、真実と語りとの間の距離が強調されフィクション性が暗示されます。また、距離が開くのはそれだけではありません。
映画『アラジン』を通して二人称形式とメタフィクションの相違点を議論した際にそれが明らかになりました。二人称は読者を物語の一登場人物として作品に「取り込む」のに対して、メタフィクションは逆に読者を物語の中に没入させず「距離をとります」。距離の演出こそがメタフィクションによる効能と言えるでしょう。
結末とはその名の通りのものなのですが、種類が二つに大別されます。ハッピーエンドやバッドエンドなどはっきりと完結する「閉じられた終わり」と、謎を残し多様な解釈を可能にする「開かれた終わり」です。
面白いのが「結末が冒頭部へ繋がり円環をなす形」、いわゆる「ループもの」もこれに当てはまるのですが、これも開かれた終わりなのだそうです。円を作っているから閉じていると思われがちなのですが、よくよく考えればきっぱり終わっているわけではないので開かれた終わりだと結論づけました。
少し休憩を挟み、次は五限。ここがこのゼミにとっての八甲田山、死の彷徨の始まりです。今回はジュリア・クリステヴァの『セメイオチケ1』について議論しました。
これは上述した「間テクスト性」の概念をさらに拡大させた話となっています。
そもそも一つのテクストにおいて引用される他のテクストは数え切れないぐらい膨大です。そうした人文科学的な構築物はそれ自体の構造が存在しているのではなく、文学テクストや歴史、社会などの他の構造と照らし合わせて形成されるというモデルが存在しています。つまり人文科学の構造を読み解くことは世界の構造を読み解くことであると言っても過言ではありません。
さらにこうして影響を与える関係は「過去作→現在作」と一方的なものであると思われがちなのですが、実は相互に影響を与えるものなのです。議論中に上がった例としては『フランケンシュタイン』と『屍者の帝国』の関係が挙げられます。後者が人造人間というモチーフを受けたのは明らかなのですが、逆にそこで描かれるテーマが前者のイメージを拡張させることにも繋がるのです。
さらに歴史というテクストについても言及されています。もともと我々が普段触れているのは歴史家が選びとった歴史の断片に過ぎません。つまり歴史家はその点において作家よりも権威を持っているということになります。ですがこの文章では、作家が読むことや書くことを通して歴史に参加することができる、つまり作家は歴史家よりも歴史に関わることができると主張しているのです。さっきからこの作者ロックなこと言ってますよね。
ここまで議論して、残念なことに時間切れになってしまいました……。つまり続きは合宿に持ち越しとなります。
さぁ、一体支払うべきツケはどこまで溜まるのか。俺たちに明日はあるのか。これは今後の頑張り次第となるでしょう。
今回の内容はここまで、次回もどうかご贔屓に。以上、内藤ゼミからでした!
タイトル
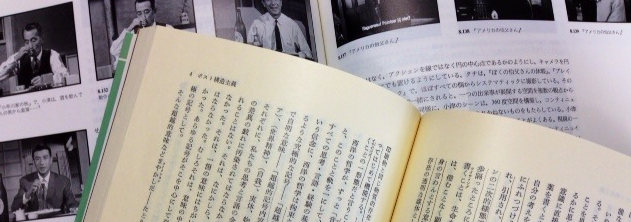
6.21.2016
6.12.2016
春学期第7回ゼミ
はじめまして、今回のブログ執筆を担当する室です。
突然ですが、今年度からこちらのブログを移設することを検討中です。
今回は議論に入る前に、その件について話し合いました。
ブログ形式だと古いものはどんどん流れて行ってしまうので、残したい情報を別ページで残しやすい形式にできるよう、計画しています。
さて、今回扱った分野は『批評理論入門』からⅠ-11「反復」とⅠ-12「異化」、そしてヴィクトル・シロフスキィの『手法としての芸術』です。
まず、『批評理論入門』の「反復」について。「反復」は音や語句などを繰り返し用いるという修辞技法で、フランケンシュタインにおいては出来事、人物、言葉、イメジャリーなど、様々な要素が反復されていました。『批評理論入門』では、これによって作品全体のテーマや雰囲気が統一されていたことが指摘されています。
議論の内容ですが、まず「韻を踏んだ反復にはどのような意味があるのか?」という疑問が挙がりました。
フランケンシュタインにおいても、原文では韻を踏んだ反復をするセリフなどがありました。これがいったいどのような意味を持つのか、ということで、他にもいろいろな反復を例に挙げて考えてみました。
同じ音が続くことで、印象に残りやすい、覚えやすいといった効果があるのではないか?という意見が出ました。スピーチなどでも韻を踏まれることはありますね。
また、詩などでは音の反復が多く使われることもあります。逆に同じような言葉が続きすぎると退屈に感じることもあることから、快や不快といった感情にも影響があるのではないか、という話でまとまりました。
次に内容を確認していきました。
フランケンシュタインでは、「死」や「怪物との出会い」のシーンが、同じような状況で繰り返し起こります。これによって、読者は「また怪物が現れるのではないか」と感じるようになっていました。また、繰り返し行われることによって、没入感が生まれるのではないか?という話も出てきました。繰り返し何度も語られると、本当にあるのではないか、と思えてきます。フランケンシュタインにおいては、「反復」は恐怖をあおる役割も担っていたのですね。
人物についても、例えば作中で女性たちは同じ目に遭います。なぜ女性ばかりが同じ目に遭うのか、ということですが、ここで「人物の反復」について話し合いました。
「歌舞伎」や戦隊ものでは、例えば二枚目がイケメン、レッドがリーダー、などの決まり事があります。人物の反復によって、ステレオタイプが作られるようです。
次に言葉の反復についてですが、フランケンシュタインでは、同じようなテーマの言葉が繰り返し用いられていました(破壊、運命、創造・・・など)。これによって作品のテーマが強調されていました。また、「生」と「死」という同等レベルのテーマが繰り返し用いられることによって、「生」という本来めでたいはずの出来事が「死」によって薄れていきました。これも、「命の創造」という出来事が悲劇的な結果につながったフランケンシュタインのテーマを強調しています。
次の分野は「異化」です。これは『批評理論入門』においては、「普段見慣れた事物から、その日常を剥ぎ取り、新たな光を当てること」と説明されています。
フランケンシュタインでは、私たちが当たり前だと思っている物事が、知識のない怪物の言葉で説明されることによって「異化」されていました。例えば誕生直後の回想において、夜の闇などが怪物の言葉で説明されています。また、初めて見た「人間」を異化するほか、「言葉」に対する驚きも異化されました。
「異化」については、5限の『手法としての芸術』で詳しく議論しました。
この中で説明されていた「異化」について、まず二つの疑問点が挙がり、そちらを議論してから内容の確認に入りました。疑問は、「人間以外の知覚を通して異化されている小説は『ホルストメール以外にもあるのか?」「大人の知覚を通して異化することは、子どもや人間以外の動物を通して異化することに比べて困難か?」ということです。
前者は、たくさん例がみつかりました。また、小説以外のメディアでも使われている場面が多くあることが分かりました。
後者についても、『テルマエ・ロマエ』など、大人の知覚を通して異化される作品があることが分かりました。この二つは、どのような対象を異化したいのかによって使い分けられているのではないかという話をしました。
さて、内容の確認ですが、まず「異化」について、「飲み物の缶を異化してみる」ということに挑戦してみました。絵で描いてみる、形を説明する、違うものに例えて説明する、素材を説明するなど、いろいろなパターンが出てきました。これによって、「異化」することで人によって様々な認識が生まれる、ということが感じられ、理解がしやすくなったと思います。
本文の中でも理解に特に苦しんだのが、「芸術の目的は、再認=それと認めることのレベルではなく直視=見ることのレベルで事物を感じとらせることにある。」「芸術の手法とは、事物を<異化>する手法であり、形式を難解にして知覚をより困難にし、長びかせる手法である。」の二文で、これについてどういう意味なのかを議論しました。
・「芸術の目的は、再認=それと認めることのレベルではなく直視=見ることのレベルで事物を感じとらせることにある。」
直視というのは、「あるがままに、目に見える通り」に物事を見ることです。繰り返されることによって、習慣化、自動化された物事は、そのあるがままの姿を見るということが難しくなってしまいます。そういった事物に対して、それ自体の姿をきちんと見ること、これが芸術の目的である、ということが書かれています。また、異化は強烈な存在感を生み出します。自動化されることによって、気にも留めなくなってしまった(=再認)ものを、異化することでそのものをきちんと見ようとする(=直視)ことができます。
・「芸術の手法とは、事物を<異化>する手法であり、形式を難解にして知覚をより困難にし、長びかせる手法である。」
「形式を難解にして知覚をより困難にし、長びかせる手法」というのが、異化です。これによって、「何だろう?」と思い続けるのが芸術だそうです。例えば現代アートでは理解されることを拒みますが、これによってそれを見る私たちは、「直視」せざるを得なくなります。見る人が理解をしてしまうことが芸術の終わりであり、そのものを理解しようといろいろな想像をすることが芸術だ、ということです。
ここで、「異化」の体験について話し合いましたが、そこで「時間の感覚」というものが出てきました。その時々で、時間は長く感じたり、あっという間に感じたりするものです。これは普段私たちが、当然「計量化」できると思っているものですから、そういった体験をするとはっとしますよね。軽量化できると思っていても、実際には歪むもので、それを気づかせてくれるのが異化です。
今回の議論は、ここで終了しました。きちんと話し合えていない部分が出てしまい、その部分に関しては合宿でまた議論をすることになっています。それにしても、難しかった・・・。
6.06.2016
春学期第6回ゼミ
はじめまして。今回のブログ執筆を担当させていただきます。提中です。珍しい苗字ですが、この漢字で(だいなか)と読みます。
今回は冒頭に夏合宿の相談を少ししてから、議論に移りました。今年は大学のセミナーハウスに宿泊をして、合宿をする計画です。既に合宿でやらなければいけないことが沢山あって、今から不安な気持ち半分、楽しみな気持ち半分の複雑な心境です。
では、さっそく本題の授業の内容紹介に移りたいと思います。今回は、『批評理論入門』第一部より「声」「イメジャリー」、またミハイル・バフチンの『ドストエフスキーの詩学』について議論を行いました。
まず、『批評理論入門』の第一部「声」についてです。作品を形作る意識や声によって、物語言説の特徴は二つに分類できます。作者の単一の意識と視点によって統一されている状態を「モノローグ的」といいます。それに対して、多様な考えを示す複数の意識や声が、それぞれの独自性を保ったまま互いに衝突する状態を「ポリフォニー的(対話的)」といいます。あらゆる小説は、ポリフォニー的な物語言説を持っています。ここで、モノローグ的な小説は存在しないのか?ということが議論になりました。その答えは、5限の『ドストエフスキーの詩学』の方のテキストにありました。どうやらドストエフスキーの小説より前の作品では、小説はモノローグ的だったようです。しかし、私たちはあまりモノローグ的な小説に出会ったことがなく、具体的な作品が思い浮かばず、理解に苦戦しました…。
今回の発表は、内容が近かったため、4限のテキストと5限のテキストを同時に行ったのですが、ポリフォニーについては、ミハイル・バフチンの『ドストエフスキーの詩学』に詳しく書かれていました。ドストエフスキーは小説において、ポリフォニー的な世界を構築し、ドストエフスキー以前のモノローグ的な小説を破壊しました。ドストエフスキー以前の小説の登場人物は、作者の意見を導くための存在でしかなく、独立した人間ではありませんでしたが、ドストエフスキーの小説の登場人物は、単なる作者の分身ではなく、それぞれが異なる世界を持っており、独立した存在です。登場人物が、生きている人間、人権を持っている人として、リアルに描かれているため、それらの登場人物たちの声は、作者の言葉と全く同等の、十全の重みを持つわけですね。また、第三回の5限の授業で扱ったロラン・バルトは、登場人物は必ずしも作者の意思に支配されているわけではないといい、バフチンの影響を受けているということが伺えます。
次は、批評理論入門の第一部「イメジャリー」についてです。想像力を刺激し、イメージを喚起する作用をイメジャリーと呼びます。イメジャリーには様々なものがありますが、批評理論入門では、「メタファー」「象徴」「アレゴリー」の3つのイメジャリーについて書かれていました。「メタファー」については後に詳しく触れるのでいったん置いておきます。「象徴」とは、あることを示すために、特に類似性のないものから連想されるものを暗示することです。『フランケンシュタイン』では、重要な場面の前後に「月」が描かれています。キリスト教において月は母性の象徴で、フランケンシュタインの創造行為や、怪物との親子関係を象徴しているともいえます。また、月はフランケンシュタインと怪物の対面に場面に繰り返し現れ、怪物が現れるたびにフランケンシュタイン達は心を乱すため、狂気の象徴でもあります。
さて、「メタファー」についてですが、授業では、批評理論入門に書かれていなかった「メトニミー(換喩)」「シネクドキ(提喩)」についても考えました。「メタファー(隠喩)」は、あることを示すために別のものとの共通性を暗示することです。例えば、「白雪姫」は雪のように白い肌のお姫様で、雪とお姫様には「白い」という共通性があります。この共通性はお姫様全体を表しています。それ対して、「メトニミー(換喩)」は赤ずきんの頭巾のように一部を持って全体を表す比喩です。「シネクドキ(提喩)」は上位概念を下位概念で、またその逆で下位概念を上位概念で言い換えることをいいます。例えば、「人はパンのみに生くるにあらず」という言葉は、人は食料を食べることだけを目的として生きているのではないという意味ですが、ここでの「パン」(下位層)は「食料」(上位層)で言い換えられています。
イメジャリーには様々な種類があって、ひとつひとつ理解するのに時間が掛かってしまいました…。
内容をまとめるのが上手くなく、長々とした文章で申し訳ありませんでした。ここまで読んでくださり、ありがとうございます。内藤ゼミではこれから文章を書く機会が沢山あるので、書く力を鍛えていきたいです。
登録:
投稿 (Atom)