今回のブログを担当させていただきます相田です。
更新が遅れてしまい大変申し訳ありませんでした。
さて、今回の会議はゴールデンウイーク明けということで、その思い出話から始まりました。
大層素敵な思い出を持っているのだろうと思いきや、5人中3人が授業の課題の美術館訪問ぐらいしかしていないと…
斯くいう自分も教習所しか言っていないのですが…
夏休み明けの思い出話には期待してください!!!
そんなことでゼミの会議の内容です。
はじめに『批評理論入門』第一部より、「語り手」と「焦点化」,「提示と叙述」の発表をしてもらいました。以下レジュメです。
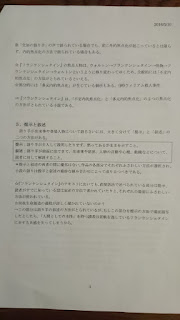
物語には原則として語り手がおり、その語りにもいくつかの手法があります。
大部分が一人称か三人称の語りですが、稀にある二人称の語りというものがどんなものなのかわからず、5人で頭をひねっていました。
また、語り手の形式にも、枠物語と書簡体物語という、2種類の分類方法があります。
ちなみに『フランケンシュタイン』は三人称と一人称の語りがあり、書簡体物語の中に枠物語が組み込まれている複雑な構造をしています。
加えて、語り手にも、信頼できる語り手と信頼できない語り手がいます。私たちもこの信頼できる語り手にはどんなものがあるかに悩まされました。ロボットみたいにすべての事象を細かく客観的に語ることができたら信頼できるのかとも思いましたが、明確な答えは出ない、というか自分たちもそれを判断できないのではないかなど、なかなか泥沼な議論だった気もしますね…
焦点化では、「見る」という行為を「焦点化」という概念で規定し、見ている主体を「焦点人物」と名付けられていることを学びました。そして、この箇所は追加テキスト『物語のディスクール』のほうでも取り上げられている話題でしたので、そちらも踏まえて議論を行いました。以下レジュメです。
最後は提示と叙述でした。
黙ってあるがままを記述する提示と語り手が心情なども踏まえて記述する叙述の2種類の方法のことですが、これは比較的スムーズに議論が進行しました。叙述には推理小説でいうところの「叙述トリック」なるものもありましたし、神の視点、つまり三人称の語りからの提示というのは理解しやすかったです。
以上で今回の会議は終了しました。今回の議論は全員が理解しているか確認しながら、一歩ずつ進まないと理解できないような内容で、自分の頭をフル回転させたような気がしました。次回もジュネット先生の追加テキストですので、難解な回になる予感がします。
それでは次回もまたお会いしましょう!!
:余談ですが、レジュメは自分の物をあげているのでところどころメモがあります。申し訳ありません。それにしても追加テキストのレジュメの下のほう、「理想の女の子→内面なんて知るか」とは、いったい何でこんなことを自分は書いたのでしょうか?:






0 件のコメント:
コメントを投稿